| 浮世絵 座敷芸 |
 |
 |
 |
||
| 浮世絵トップページ | テーマ別浮世絵・絵草子一覧 | 天竺老人トップページ |
| 座敷芸 |
| 踊・演芸 | 唄・三味線 | 軽口咄・落噺 | 座敷遊び |
| 座敷芸は一般的には酒宴の席などで場を盛り上げるために演じる芸のことを言うようですが、このページでは言葉の定義に関わらず江戸時代に出版された主として座敷や少人数の集まりの場所でで演じられたと思われる各種の芸能、遊びに関わる浮世絵、絵草紙などを掲載しています。 掲載作品の中で量的にもっとも多いのは落語に関するものです。日本の伝統話芸である落語は今昔物語や宇治拾遺物語などの滑稽話、説話などにその源流が見られるという。ただし職業としての噺家が出現するのは江戸時代になってから。娯楽の乏し時代の手軽な楽しみとしてに庶民の人気を集めたようです。当初は芝居小屋や風呂屋、あるいは料理茶屋などの座敷に呼ばれて座敷芸の形で行われていたが、江戸後期には現在見られる形の寄席も出現したようです。落語は”落ちのある滑稽な噺(話)”が語源ですが、江戸時代には「落語(らくご)」という表現はされず、軽口噺、座敷噺、落噺(おとしばなし)などと呼ばれていた。 量的には僅かですが座敷芸としての踊りや演芸、座敷遊びに関する絵入の出版物や浮世絵も掲載していますのでご覧ください。 |
| 踊・演芸 |
 |
座敷舞台 華袖笠 絵: 作: |
出版年: 版元:村田次郎兵衛 黒本 2冊 |
||
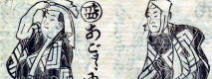 |
踊独稽古 絵:葛飾北斎 作:藤間新三郎 |
出版年:文化12年(1815) 版元:鶴屋金助 絵手本 1巻 |
 |
おどりづくし 絵: 作: |
出版年: 版元: |
 |
物真似草紙 絵:東西庵南北 作:東西庵南北 |
出版年:文化12年(1815) 版元:西村新六 合巻 2冊 |
 |
座敷芸茶番の当振 絵:三代歌川豊国 作: |
出版年:弘化4年(1847)~嘉永5年(1852) 版元:ゑびすや 浮世絵 |
||
| ページトップ |
| 唄・三味線 |
 |
長唄こきんしう 絵: 作: |
出版年:天和2年81682) 版元: 演芸本 1巻 |
 |
はやり歌古今集 絵: 作: |
出版年:元禄12年(1699) 版元: 演芸本 1巻 |
 |
享保よみ売はやり唄 絵: 作: |
出版年:享保年間(1716~1735) 版元: |
 |
時花唄 絵: 作: |
出版年: 版元: |
 |
恋合端唄尽 絵:三代歌川豊国 作: |
出版年:文久1年(1861) 版元:和与 浮世絵 |
| ページトップ |
| 軽口咄・落噺 |
 |
噺物語 絵:吉田半兵衛 作:幸佐 |
出版年:延宝8年(1680) 版元:満足屋清兵衛 咄本 3巻 |
||
 |
武左衛門口伝咄 絵:菱川師宣 作:鹿野武左衛門 |
出版年:天和3年(1683) 版元:鱗形屋 咄本 2巻 |
 |
けらけらわらひ 絵: 作: |
出版年:貞享年間(1684~1687) 版元: 咄本 2巻 |
 |
枝珊瑚珠 絵:石川流宣 作:石川流宣 |
出版年:元禄3年(1690) 版元:相模屋太兵衛 咄本 5巻 |
 |
正直咄大鑑 絵:菱川師宣 作:石川流宣 |
出版年:元禄7年(1694) 版元:万屋清兵衛 咄本 5巻 |
||
 |
座敷ばなし 絵: 作:夜食時分 |
出版年:元禄10年(1697) 版元:伊丹屋太郎右衛門 咄本 5巻 |
||
 |
露五郎兵衛新はなし 絵: 作:露五郎兵衛 |
出版年:元禄14年(1701) 版元:菱屋治兵衛 咄本 1巻 |
 |
露休かへり花 絵: 作:露五郎兵衛 |
出版年:正徳2年(1712) 版元:田井利兵衛 咄本 5巻 |
 |
やぶに万久和 絵: 作: |
出版年:享和3年(1718) 版元:敦賀屋久兵衛 咄本 5巻 |
 |
軽口機嫌袋 絵: 作:松泉 他 |
出版年:享保13年(1728) 版元:万屋作右衛門 咄本 5巻 |
||
 |
軽口福徳利 絵: 作:応斎、玉花 |
出版年:宝暦14年(1764) 版元:河内屋吉兵衛 咄本 5巻 |
||
 |
軽口大矢数 絵: 作:米沢彦八 |
出版年:宝暦年間(1751~1763) 版元: 咄本 1巻 |
 |
軽口もらいゑくぼ 絵: 作: |
出版年:明和8年(1771) 版元;安井弥兵衛 咄本 5巻 |
||
 |
春遊機嫌袋 絵:恋川春町 作: |
出版年:安永4年(1775) 版元:鱗形屋孫兵衛 咄本 |
 |
新落噺初鰹 絵:富川吟雪 作: |
出版年:安永5年(1776) 版元:鶴屋 咄本 3巻 |
||
 |
初笑福徳噺 絵:鳥居清経 作: |
出版年:安永5年(1776) 版元: 鱗形屋孫兵衛 咄本 1巻 |
||
 |
夜明茶呑噺 絵:鳥居清経 作: |
出版年:安永5年(1776) 版元:鱗形屋孫兵衛 咄本 2巻 |
||
 |
落咄福来樽 絵:鳥居清経 作: |
出版年:安永7年(1778) 版元: 咄本 2巻 |
||
 |
友たちはなし 絵:鳥居清経 作: |
出版年: 版元:伊勢屋治助 咄本 2巻 |
 |
寿々葉羅井 絵:北川豊章(歌麿) 作:志丈 |
出版年:安永8年(1779) 版元:竹川藤助 咄本 1巻 |
 |
菊寿盃 絵:北尾政美 作:伊庭可笑 |
出版年:天明1年(1781) 版元:村田屋次郎兵衛 咄本 3巻 |
 |
御無文字片沓話 絵:北尾政美 作: |
出版年:天明4年(1784) 版元: 黄表紙 2冊 |
 |
昔々噺問屋 絵:北尾政美 作:恋川好町 |
出版年:天明5年(1785) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 1冊 |
||
 |
爐開噺切口 絵:喜多川歌麿 作:浮世伊之助 |
出版年:寛政1年(1789) 版元: 咄本: |
||
 |
笑府衿裂米 絵:北尾政美 作:曲亭馬琴 |
出版年:寛政5年(1793) 版元:蔦屋重三郎 咄本 1巻 |
||
 |
花袋伝 絵:十返舎一九 作:十返舎一九 |
出版年:寛政9年(1797) 版元:三河屋小兵衛 咄本 1巻 |
 |
戯聞塩梅余史 絵:子興(栄松斎長喜) 作:曲亭馬琴 |
出版年:寛政11年(1799) 版元: 咄本 1巻 |
 |
新作咄太郎花 絵:北尾政美 作:山東京伝 |
出版年:寛政年間 版元:蔦屋重三郎 咄本 2巻 |
||
 |
落咄福種蒔 絵: 作:遠唐沖人 |
出版年:享和1年(1801) 版元: 咄本 2巻 |
 |
豊年はなし 絵: 作:鈍々亭和樽 |
出版年:享和1年(1801) 版元: 咄本 1巻 |
 |
笑嘉登 絵:喜多川月麿 作:立川銀馬 |
出版年:享和1年(1801) 版元:西村屋与八 咄本 1巻 |
 |
七福今年咄 絵:歌川豊広 作:桜川慈悲成 |
出版年:享和2年(1802) 版元:西村屋与八 咄本 2冊 |
 |
一粒撰噺種本 絵:歌川豊広 作:桜川慈悲成 |
出版年:享和2年(1802) 版元:西村屋与八 咄本 3冊 |
 |
遊子戯語 絵:歌川豊広 作:桜川慈悲成 |
出版年:享和3年(1803) 版元:山林堂三四郎 咄本 1巻 |
||
 |
軽口噺 絵:(歌川)貞之 作:十返舎一九 |
出版年:享和3年(1803) 版元:和泉屋市兵衛 咄本 1巻 |
||
 |
咄の開帳 絵:鳥居清経 作:蔦の唐丸 |
出版年:享和3年(1803) 版元: 咄本 1巻 |
||
 |
落噺百夫婦 絵:喜多川秀麿 作:並木丹作 |
出版年:文化1年(1804) 版元: 咄本 1巻 |
 |
洗濯こうしや 絵:北尾政美 作: |
出版年: 版元: 咄本 2巻 |
||
 |
落咄常々草 絵:歌川豊国 作:桜川慈悲成 |
出版年: 版元: 咄本 1巻 |
||
 |
落咄屠蘇機嫌 絵:歌川国丸 作:十返舎一九 |
出版年:文化14年(1817) 版元:鶴屋喜右衛門 咄本 3巻 |
||
 |
耶津天御覧 絵:勝川春亭 作:十返舎一九 |
出版年:文化14年(1817) 版元:丸屋文右衛門 咄本 3巻 |
 |
噺の親玉 絵:歌川豊広 作: |
出版年:文化15年(1818) 版元: 咄本 1巻 |
||
 |
落咄通人蔵 絵:歌川国丸 作:立川焉馬 |
出版年: 版元: 咄本 1巻 |
 |
落噺笑竹 絵:勝川春亭 作:文尚堂虎円 |
出版年:文政3年(1820) 版元:丸屋文右衛門 咄本 1巻 |
||
 |
落噺生鯖船 絵:柳川重信 作:玉虹楼一泉 |
出版年:文政3年(1820) 版元:西村屋与八 咄本 1巻 |
 |
仕形落語 工夫智恵輪 絵:二代勝川春好 作:東里山人 |
出版年:文政4年(1821) 版元:和泉屋市兵衛 咄本 1巻 |
 |
葉南志廼生簀 絵:歌川国丸 作:欣堂間人 |
出版年:文政5年(1822) 版元:森屋治兵衛 咄本 3巻 |
 |
江戸自慢 絵: 作:三笑亭可楽 |
出版年:文政6年(1823) 版元:山口屋藤兵衛 咄本 1巻 |
 |
洒落口乃種本 絵:歌川広重 作: |
出版年:文政10年(1827) 版元:伊藤与兵衛 咄本 2巻 |
 |
延命養談数 絵:歌川国貞 作:桜川慈悲成 |
出版年:天保4年(1833) 版元:山本平吉 咄本 4巻 |
 |
落噺笑富林 絵:二代北尾重政 作:林家正蔵 |
出版年:天保4年(1833) 版元:西村屋与八 咄本 2巻 |
 |
百歌撰 絵:歌川貞秀 作:林家正蔵 |
出版年:天保5年(1834) 版元:西村屋与八 咄本 2巻 |
 |
落咄年中行事 絵:歌川貞秀 作:林家正蔵 |
出版年:天保7年(1836) 版元:西村屋与八 咄本 2巻 |
 |
春興福神咄 絵:歌川国芳 作:柳下亭種員 |
出版年:弘化1年(1844) 版元:錦彩堂虎松 咄本 1巻 |
| ページトップ |
| 座敷遊び |
 |
七拳図式 絵: 作:四方赤良 |
出版年:安政8年’1779) 版元:西村源六 滑稽本 1巻 |
 |
拳会角力図会 絵: 作: |
出版年:文化6年(1809) 版元:河内屋太助 遊戯本 2巻 |
 |
曲扇興図式 絵: 作: |
出版年:安永2年(1773) 版元: 遊戯本 1巻 |
 |
投扇新興 絵: 作:輪台山人 |
出版年:安永2年(1773) 版元: 升屋文蔵 遊戯本 1巻 |
 |
投扇興譜 絵: 作: |
出版年:安永3年(1774) 版元:上総屋利兵衛 遊戯本 1巻 |
| ページトップ |
| 絵: 作: |
出版年: 版元: |
| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |