| 浮世絵 赤本 |
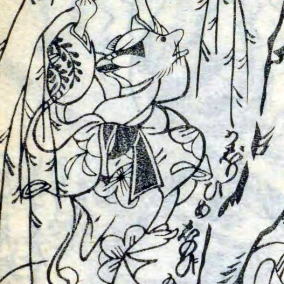 |
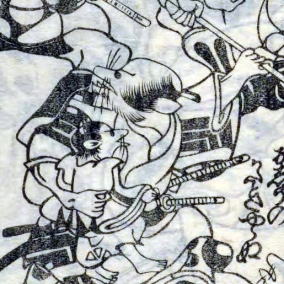 |
 |
||
| 浮世絵トップページ | 版本目録 | 天竺老人トップページ |
| 赤本(あかぼん) |
| 江戸時代になると印刷技術(木版印刷・版画)が進歩・普及して上方を中心として御伽草子や仮名草子の出版が活発となる。江戸でも寛文(1661~)の頃から子供向けの絵本などが出版されるようになる。対象が子供向けであることから表紙は目立つように赤色にしたようだ。これを赤本(あかほん・あかぼん)といった。当初はお伽噺、民話などを題材とした絵が中心の読み物であったが次第に内容も広がり、武勇伝や合戦物、風俗や浄瑠璃などに題材を得たものが出版されるようになると赤い表紙の体裁では内容とそぐわなくなり、表紙を黒(黒本)あるいは萌黄色(青本)に変化させていく。これらの出版物は(これ以後に出版される黄表紙・合巻も含めて)一括りに「草双紙(くさぞうし)」と呼称されることも多い。一般的には子供向けの絵本を赤本といい、大人向けを黒本、青本とする。赤本、黒本、青本ともに縦約18cm、横約13cmの中本型であること。5丁(10頁)を一冊とすること。また絵(挿絵)が中心で文章はその説明程度であることが共通している。 赤本は元禄期(1688~)から享保期(1716~)に最盛期を迎え、寛延年間(1748~)まで刊行された。しかし赤本は子供の日常用品としての性格から現存品は少ないようだ。江戸後期になって赤本を復活させようとする動きがあり、浮世絵を描いた赤色を基調とした表紙の赤本が出版された。 |
 |
初春のいわい 絵:菱川師宣 作: |
出版年:延宝6年(1678) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
俳諧一字題地口 絵:羽川沖信 作: |
出版年:享保8年(1723) 版元:いが屋 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
さるかに合戦 絵:西村重長 作: |
出版年:享保年間(1716~1735) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
ねずみの嫁入 絵:西村孫三郎(石川豊信) 作: |
出版年: 版元: 赤本 2冊 |
 |
富貴長命丸 絵:近藤清春 作: |
出版年:享保年間(1715~1735) 版元: 赤本 1冊 |
||
 |
祢こ鼠大友のまとり 絵:近藤清春 作: |
出版年:享保年間(1715~1735) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
ぶんぶくちゃがま 絵:近藤清春 作: |
出版年:享保年間(1715~1735) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
鼠花見 絵:近藤清春 作: |
出版年:享保年間(1715~1735) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
いろはたんか 絵:近藤清春 作: |
出版年:享保年間(1715~1735) 版元: 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
五百八十七曲 絵: 作: |
出版年:江戸中期 版元:鱗形屋 赤本 2冊 |
||
 |
千本左衛門 絵: 作: |
出版年:江戸中期 版元: 赤本 3冊 |
||
 |
はちかつきひめ 絵: 作: |
出版年:江戸中期 版元:鱗形屋 赤本 2冊 |
||
 |
塩売文太物語 絵: 作: |
出版年:寛延2年(1749) 版元:鱗形屋 赤本 2冊 |
||
 |
枯木に花咲せ親父 絵: 作: |
出版年:寛延年間(1748~1750) 版元:鱗形屋 赤本 1冊 現存本ではなく希書複製会刊行の複製本 |
||
 |
鬼の四季あそび 絵:歌川国丸 作: |
出版年:江戸後期 版元: 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
源平盛衰記 絵:歌川国信 作: |
出版年:江戸後期 版元:鶴屋金助 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
古今武者揃 絵:歌川広重 作:夷福山人 |
出版年:江戸後期 版元:佐野喜 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
舌切雀 絵:溪斎英泉 作:可候 |
出版年:江戸後期 版元:山本 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
往昔舌切雀 絵:歌川広重 作:夷福山人 |
出版年:江戸後期 版元:佐野喜 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
猫鼠合戦 絵: 作: |
出版年:江戸後期 版元: 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
桃太郎 絵:歌川国丸 作:桜川慈悲成 |
出版年:江戸後期 版元: 赤本(復興版) 2冊 |
||
 |
桃太郎宝蔵入 絵:歌川広重 作:夷福山人 |
出版年:江戸後期 版元:佐野喜 赤本(復興版) 2冊 |
||
| ページトップ |
| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |